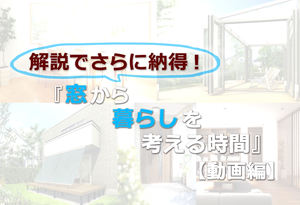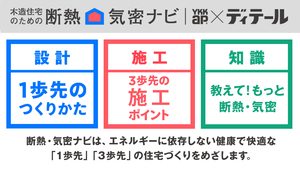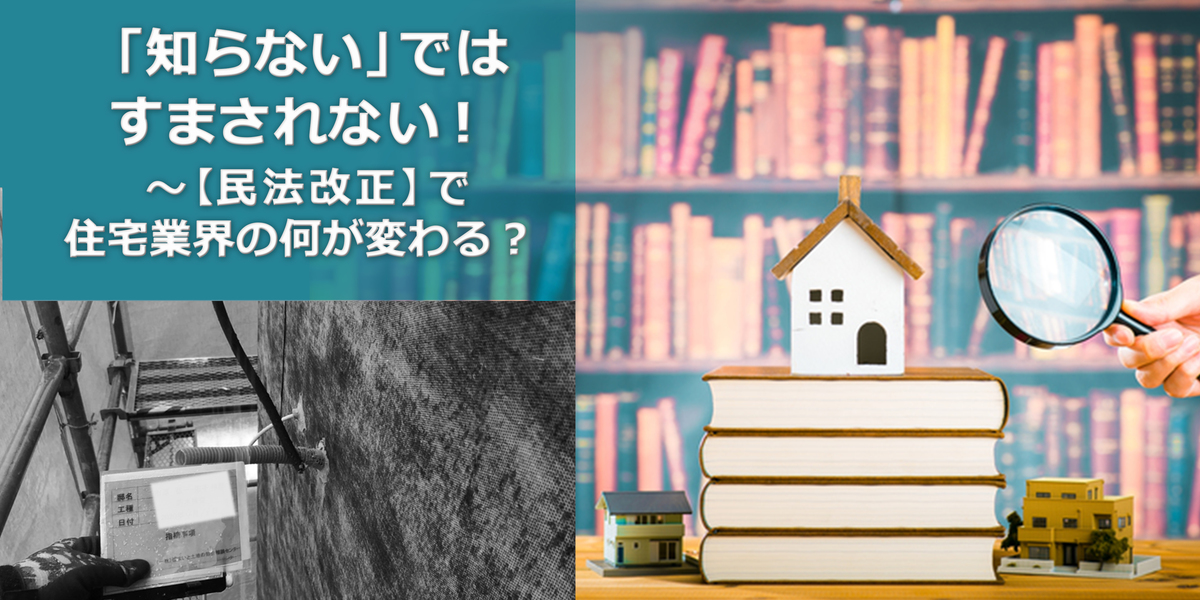 インスペクターが考える民法改正【その8】です(前回記事はこちら)今回は防水検査フィードバックのお話です。検査タイミングは防水紙完了し、胴縁施工や貫通部の施工が完了した段階です。防水検査では、何と言っても「貫通部の施工不適」の指摘が目立ちます。写真はハウスメーカー各社のものです。ハウスメーカーでは貫通部の防水を防水テープのみで施工しているケースは少なく、次の写真は成型役物を使用している様子です。せっかくの役物ですが、破損しているのがわかります。一般の工務店さんでも成形品(例えばフクビのウェザータイトなどが有名でしょうか)を採用していることが多いとは思いますが、意外にメーカー施工マニュアル通りに施工されていないことも見かけます。役物を使えば大丈夫ではなく、施工マニュアル通りに正しく施工されていることが重要です。間違った使用方法では「契約違反」と言われる可能性が今後は高くなるでしょう。次の写真は配管の逆勾配ですね。万一、雨が入ってしまっても、雨水が外へ外へ排出されるように水勾配を外側へ取ることは基本中の基本です。特に、断熱材を発泡ウレタン仕様にしている工務店さんは、ウレタンが発泡した段階で配管が押されることがありますので、指摘数が上がります。断熱材を吹いた後で、外部の点検確認を推奨します。特に、最近では屋根通気を採用している設計計画も多いはずですから、屋根通気の潰れなども併せて確認しておきましょう。また、指摘の多い項目としては配管の複数本出しです。写真のような状況では、どんなに丁寧に防水テープを貼っても配管突合せ部で「ピンホール」が発生しますので、貫通部のルール自体を見直す必要があります。防水施工の管理で難しい(大変)のは、異業種の作業分担ではないでしょうか。屋根ルーフィングは屋根業 ..
インスペクターが考える民法改正【その8】です(前回記事はこちら)今回は防水検査フィードバックのお話です。検査タイミングは防水紙完了し、胴縁施工や貫通部の施工が完了した段階です。防水検査では、何と言っても「貫通部の施工不適」の指摘が目立ちます。写真はハウスメーカー各社のものです。ハウスメーカーでは貫通部の防水を防水テープのみで施工しているケースは少なく、次の写真は成型役物を使用している様子です。せっかくの役物ですが、破損しているのがわかります。一般の工務店さんでも成形品(例えばフクビのウェザータイトなどが有名でしょうか)を採用していることが多いとは思いますが、意外にメーカー施工マニュアル通りに施工されていないことも見かけます。役物を使えば大丈夫ではなく、施工マニュアル通りに正しく施工されていることが重要です。間違った使用方法では「契約違反」と言われる可能性が今後は高くなるでしょう。次の写真は配管の逆勾配ですね。万一、雨が入ってしまっても、雨水が外へ外へ排出されるように水勾配を外側へ取ることは基本中の基本です。特に、断熱材を発泡ウレタン仕様にしている工務店さんは、ウレタンが発泡した段階で配管が押されることがありますので、指摘数が上がります。断熱材を吹いた後で、外部の点検確認を推奨します。特に、最近では屋根通気を採用している設計計画も多いはずですから、屋根通気の潰れなども併せて確認しておきましょう。また、指摘の多い項目としては配管の複数本出しです。写真のような状況では、どんなに丁寧に防水テープを貼っても配管突合せ部で「ピンホール」が発生しますので、貫通部のルール自体を見直す必要があります。防水施工の管理で難しい(大変)のは、異業種の作業分担ではないでしょうか。屋根ルーフィングは屋根業 ..A-PLUGは工務店様・リフォーム店様などの
建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。
建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。