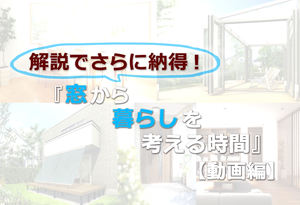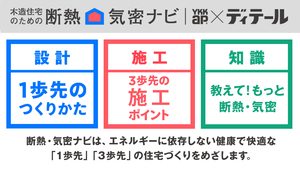(前回記事はこちら)◆前回のおさらいその2では1981年に定められた我が国の新耐震基準の2つの要求水準である①中地震に対して損傷しないこと②大地震に対して倒壊しないことについて解説しましたが、言い換えると、①中地震=建物重量の20%で、降伏点を超えない②大地震=建物重量の100%(×低減係数)で、最大荷重を超えないということで、2つの基準を満たせば安全な木造住宅を設計できることを説明しました。この設計の考え方は「保有水平耐力計算」で採用されています。保有水平耐力計算は②について直接検証する方法で、建物を横に荷重をかけて壊すことを想定したプッシュオーバー解析(前回「壊して知る耐震性能(その2)」参照)を行って、建物の壊れる様子を見て、建物が保有している耐力(保有水平耐力)が建物重量の100%の荷重×低減係数(必要保有水平耐力)を超えていることをチェックする計算方法です。保有水平耐力は柱・梁や壁などの部材が1つでも壊れるとそこが保有水平耐力とみなされます。そのため、部材を細かくモデル化してチェックする高度な解析が必要となります。高さが31mを超える建物に義務付けられている計算方法で、一般的な木造住宅で用いられることはほとんどありませんが、建物を壊して耐震性能を知ることができる手段です。◆保有水平耐力計算をやってみようwallstatではプッシュオーバー解析を実施して、保有水平耐力と必要保有水平耐力をチェックできる機能があります。必要保有水平耐力を満足しているか?保有水平耐力はどの部材の破壊で決まっているか?など、高度な検証法を身近にできる機能です。前回紹介した建築基準法ぎりぎりの壁量の解析モデルをプッシュオーバー解析してみた結果が次の映像です。計算が終了して、結果を確認すると曲線( ..
(前回記事はこちら)◆前回のおさらいその2では1981年に定められた我が国の新耐震基準の2つの要求水準である①中地震に対して損傷しないこと②大地震に対して倒壊しないことについて解説しましたが、言い換えると、①中地震=建物重量の20%で、降伏点を超えない②大地震=建物重量の100%(×低減係数)で、最大荷重を超えないということで、2つの基準を満たせば安全な木造住宅を設計できることを説明しました。この設計の考え方は「保有水平耐力計算」で採用されています。保有水平耐力計算は②について直接検証する方法で、建物を横に荷重をかけて壊すことを想定したプッシュオーバー解析(前回「壊して知る耐震性能(その2)」参照)を行って、建物の壊れる様子を見て、建物が保有している耐力(保有水平耐力)が建物重量の100%の荷重×低減係数(必要保有水平耐力)を超えていることをチェックする計算方法です。保有水平耐力は柱・梁や壁などの部材が1つでも壊れるとそこが保有水平耐力とみなされます。そのため、部材を細かくモデル化してチェックする高度な解析が必要となります。高さが31mを超える建物に義務付けられている計算方法で、一般的な木造住宅で用いられることはほとんどありませんが、建物を壊して耐震性能を知ることができる手段です。◆保有水平耐力計算をやってみようwallstatではプッシュオーバー解析を実施して、保有水平耐力と必要保有水平耐力をチェックできる機能があります。必要保有水平耐力を満足しているか?保有水平耐力はどの部材の破壊で決まっているか?など、高度な検証法を身近にできる機能です。前回紹介した建築基準法ぎりぎりの壁量の解析モデルをプッシュオーバー解析してみた結果が次の映像です。計算が終了して、結果を確認すると曲線( ..A-PLUGは工務店様・リフォーム店様などの
建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。
建築関係プロユーザー対象の会員制サイトです。